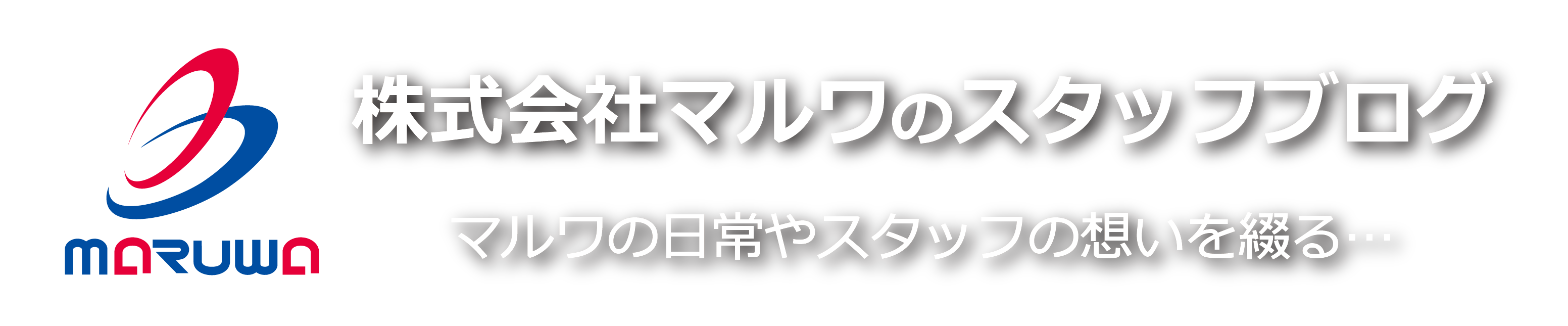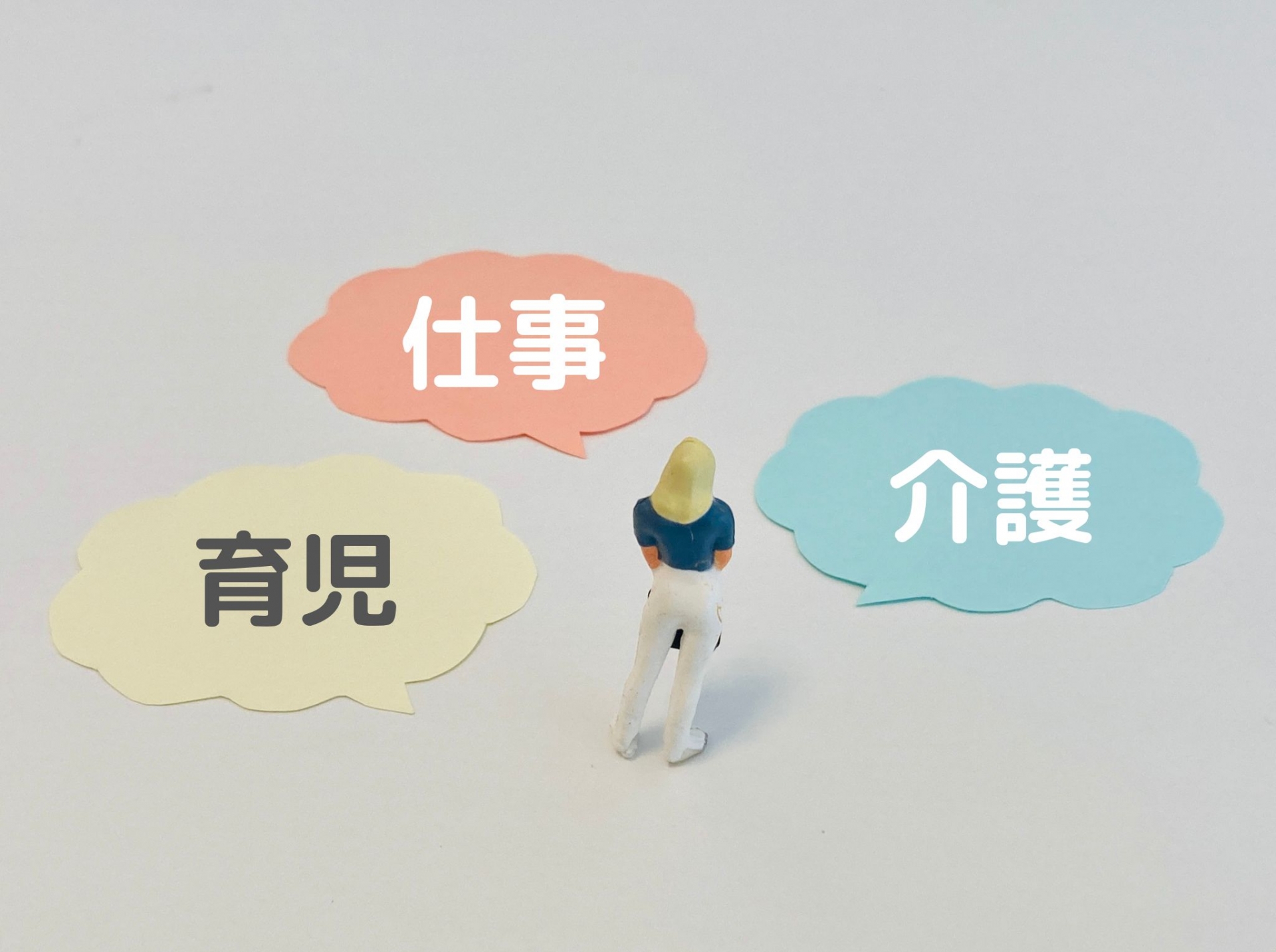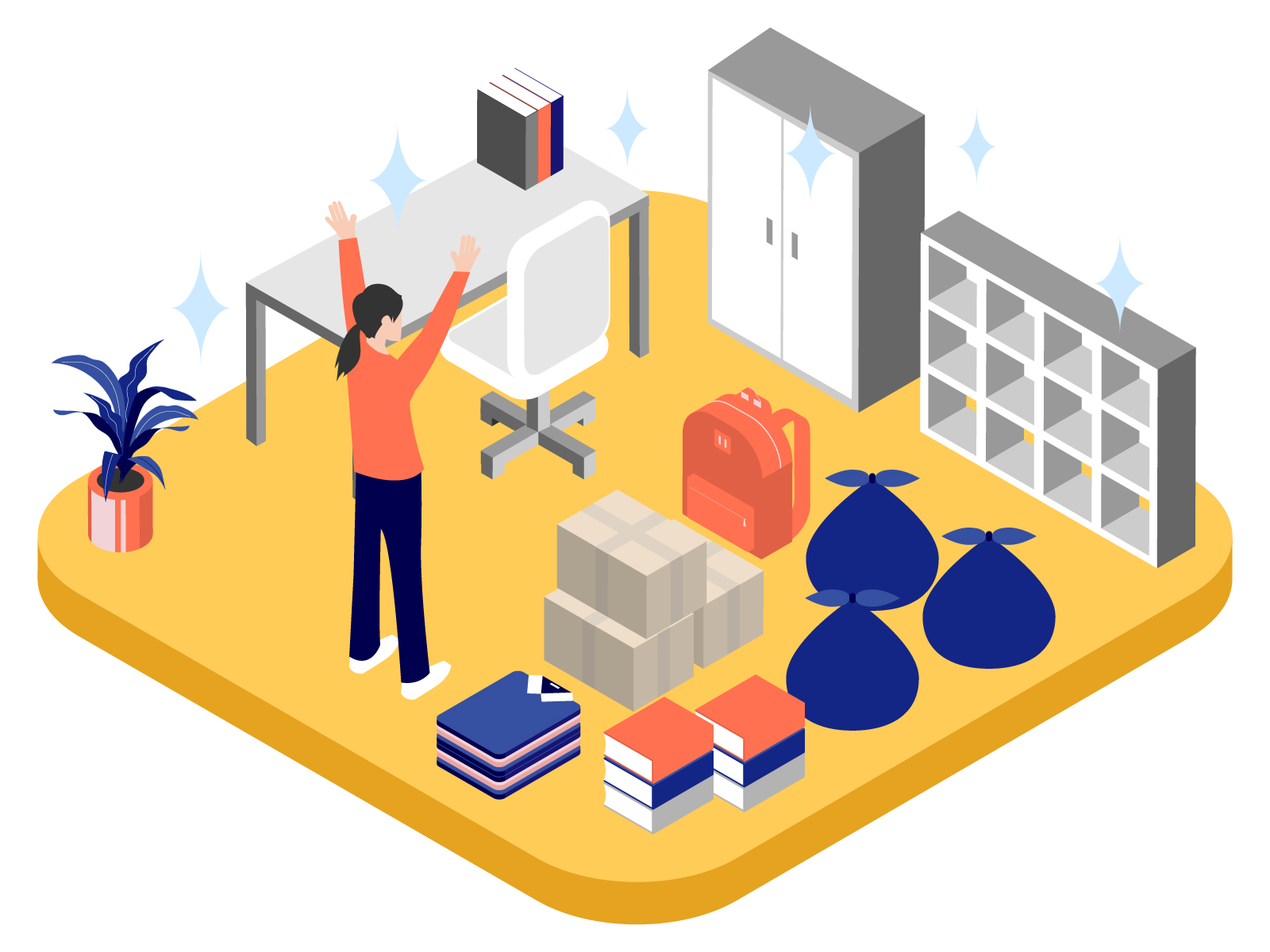「育児介護休業法」が改正され、2025年4月1日より順次施行されます。
今回の改正では制度利用対象者の範囲拡大などが含まれており、また、すべての事業者に関係してくるため、施行前に就業規則の見直しや対象となる従業員の確認などをしておく必要があります。
ということで、改正の要点などを法律ド素人が、それなりにまとめてみました、というのが今回のブログです。
どうも、マルワのシャドーサイドあれこれ担当です。
毎回になりますが、あくまでも素人まとめなので、法的に正しくない解釈が含まれている可能性はあります。詳しくは厚労省のWEBサイトや顧問弁護士さん、社労士さんなどにご確認ください。
なお、前回の育児介護休業法の改正ポイントについても以前のブログにまとめておりますので、そちらもご参照いただけますと幸いです。
参考:厚労省「令和6年改正法の概要」「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正のポイント」
労働者は育児介護に関する様々な制度が利用できる
改正内容の説明の前に、そもそもですが、育児(出産含む)や介護をしながら働く労働者は、労基法や育児介護休業法などに基づいた様々な制度を利用することができます。
| 対象者 | 制度 |
| 妊娠・出産する人 | 産前産後休業(産休) |
| 育児をしながら働く人(男女問わず) | 育児休業(男性の場合出生時育児休業もあり)、子の看護休暇、短時間勤務、所定外労働(残業)の制限、深夜労働の免除 |
| 介護をしながら働く人 | 介護休業、介護休暇、短時間勤務、所定外労働(残業)の制限、深夜労働の免除 |
これらの制度について、
- 男女ともに仕事と育児・介護を両立できるように措置を拡大する
- 育休取得状況の公表義務の拡大・次世代育成支援対策の強化
- 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化
という趣旨で法令が改正されます。
以下に今回の改正ポイントをまとめてみました。
子の年齢に応じた柔軟な働き方のための措置拡大
今回の改正により、以下の措置の実施が義務化(一部努力義務化)され、労働者はより柔軟な働き方を選択できるようになります。
| 改正内容 | 施行日 |
| 所定外労働の制限(残業の免除)の対象が「子が3歳になるまで」から「就学前(小学校入学前)の子を養育する従業員」に拡大 | 2025年4月1日 |
| 3歳未満の子を養育する者について、短時間勤務が困難な場合の代替措置に「テレワーク」を追加することが努力義務化 | 2025年4月1日 |
| 子の看護休暇の取得要件が緩和され、小学校3年生修了までの子を養育する従業員が対象となり、併せて勤続期間による適用除外の廃止、取得理由が拡充※1、「子の看護等休暇」となる | 2025年4月1日 |
| 3歳以上で小学校就学前の子を養育する労働者※2について、事業者は次の5つから2つ以上の制度を選択して措置することが義務化(労働者は事業者が選択した制度から1つを選ぶ) ・始業時刻等の変更 ・テレワーク等(月に10日) ・保育施設の設置運営等 ・新たな休暇の付与(年に10日) ・短時間勤務制度(原則6時間だが5時間や7時間など、または週休3日制にするなどの対応を設けることが望ましい) テレワークと新たな休暇は原則時間単位で取得可とする | 2025年10月1日 |
| 従業員が妊娠・出産を申し出た時、子が3歳になるまでの適切な時期(育休からの復帰時や定期面談実施時など)に、個別に制度の周知、働き方の意向確認※3を実施することが義務化 | 2025年10月1日 |
※1 従来の病気やケガ、予防接種などによる「子の看護」以外でも、感染症などで学級閉鎖で子が休む場合や、入園(入学)式・卒園式への参加の場合も子の看護等休暇の利用が可能になります。また、これまでは労使協定がある場合に認められた「勤続6か月未満労働者の制度適用除外」が認められなくなります。
※2 従来の3歳未満の子を養育する従業者への短時間勤務制度または代替措置は従来通り適用され、小学校就学前までの子を養育する労働者に対象を拡大して、柔軟な働き方を選択できるように措置を講じることが義務化されます。
※3 育休(産後パパ育休含む)取得意向、勤務時間帯・勤務地の希望、柔軟な働き方のための措置の利用期間の希望、子に障がいがある場合やひとり親の場合等による短時間勤務制度や子の看護等休暇制度の利用可能期間延長または付与日数への配慮等の必要性などを面談等で「個別」に確認しなければなりません(全体周知のみはNG)。
さらに、雇用保険法なども同時期(2025年4月1日~)に改正され、次のように子育てにかかる経済的負担を支援する制度がはじまります。
| 出生後休業支援給付 | 子の出生直後(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業の後の8週間以内)に「父母とも※4」14日以上の育休を取得した場合、28日を限度として休業開始前賃金の13%相当が支給されます。 |
| 育児期時短就業給付 | 男女問わず、2歳未満の子を養育する労働者が、養育のために時短勤務をする場合、時短勤務中の賃金額の10%が支給されます。 |
※4 ひとり親家庭の場合や配偶者が専業主婦(夫)の場合は被保険者のみが指定期間内に育休を取得すれば給付を得られます。
子育てのために時短勤務を希望したいが、収入が減るのはキツい……
または、時短からフルタイムに戻したいが残業は困る……
という労働者の負担を軽減するためにこのような制度ができた(強化された)、ということです。
企業側は、このような制度があることを対象社員に周知し、制度活用希望を確認すること、および就業規則などを法改正に適合するように整備しておきましょう。
育休取得状況公表義務の拡大・次世代育成支援対策強化
常時雇用従業員数1000人以上の企業に義務化されていた「育児休業取得状況の公表義務」の対象が、「常時雇用従業員数300人以上の企業」に拡大されます(2025年4月1日施行)。
また、「次世代育成支援対策推進法」により義務・努力義務とされている仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」の策定について、一部数値目標の設定が義務化されます(2025年4月1日施行)。
具体的には「育休取得状況(男性の育休取得率)」と「労働時間の状況(各月の時間外・休日労働時間)」の2項目について数値目標を設定することが義務化されます。
なお、「一般事業主行動計画」の策定は、常時雇用従業員数101人以上の企業については「義務」、それ以下の企業については「努力義務」とされます。
また、「次世代育成支援対策推進法」の有効期限は2025年3月31日までとされていましたが、2035年3月31日まで延長されます。
介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化
介護支援制度を活用できないまま介護を理由に離職してしまうことを防止するため、以下の事項の実施がすべての事業者に義務付けられます(2025年4月1日施行)。
- 従業員から介護に直面した旨の申出があった時点で、両立支援制度について、「個別」に周知・利用意向確認を行うこと
- 両立支援制度について、介護に直面する前の早い段階(40歳になった時点など)で、両立支援制度に関する情報を提供すること
- 研修実施、相談窓口設置など雇用環境を整備すること
- 介護期の働き方について、テレワークを選択できるようにする(努力義務)
- 介護休暇取得条件について、「勤続6か月未満」の労働者を除外しないこと(従来の適用除外制度の廃止)
制度利用者への配慮、利用者周囲の従業員への配慮
法改正の有無に関わらず、育児や介護をしながら働く人については、次のような配慮も必要です。
- プライバシーへの配慮:妊娠・出産・介護を他の従業員に知られたくない人もいるため、情報共有範囲についての本人の意向を尊重する
- 心身の健康への配慮:育児や介護のために始業時刻を変更したり、テレワークを採用したりする場合でも、夜間勤務や長時間労働になってしまわないよう、業務配分に配慮する(勤務間インターバルの適用、適切な勤怠管理の実施など)
- 制度利用者以外の労働者の心身の健康への配慮:育児や介護のために短時間勤務や残業免除、休業などする労働者と共に働くその他の従業員についても、心身の健康を損なわないように配慮する
育児や介護のために休業したり、時短勤務(残業免除)などをする従業員本人は申し訳ない気持ちを抱えてしまい、育児や介護の疲労と併せて大きな負担となってしまうことがあります。
逆に、休業や時短勤務分をカバーするために、その他の従業員が長時間労働や休日勤務を強いられたり、精神的なストレスを抱えてしまうことも避けなければなりません。
必要であれば(可能であれば)人員を補充するなどして、適正な業務量分配を維持できるように体制を整備することも不可欠です。
法令や制度が変わることで仕事と生活の両立がしやすくなるかと思いますが、なによりも大切なのは、
お互いを思いやって助け合う気持ち
ですよね!
法令で認められた制度を利用する人も、その周囲で働く人も、精神的にも肉体的にもストレスを抱えることなく、気持ちよく支え合えあっていければ、少子化(人口減少)・労働人口減少問題も少しは解消の方向に向かうのではないでしょうか(イマジン)。
企業側は、特に「義務」とされることについて、できるだけ早めに就業規則や社内体制を見直しておきましょう。
……ということで、本日の私の脳内DJのパワープッシュは、インディーPOP界の最重要人物のひとり、アメリア・フレッチャー率いる伝説のアノラックバンドTalulah Goshの名曲“Bringing Up Baby”です(曲名オンリーな選曲ではありますが)。
彼女たちの曲は、ほぼすべてDIY感あふれる3分間(未満)パンキッシュ・POPソングばかりで、どの曲も良いのですが、この曲は日本でも(一部のインディーファンの間では)有名な曲なので、お時間あるときに聴いてみてください。
本日はこの辺で。