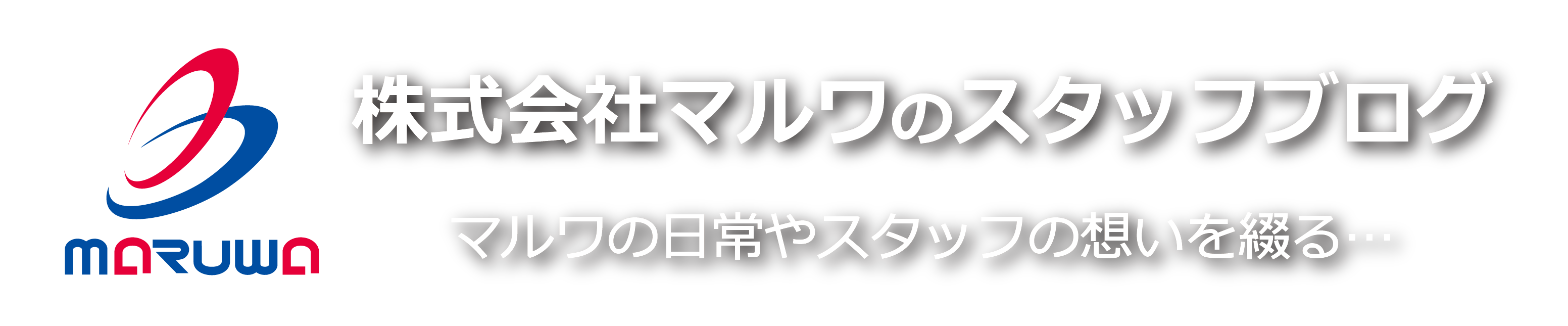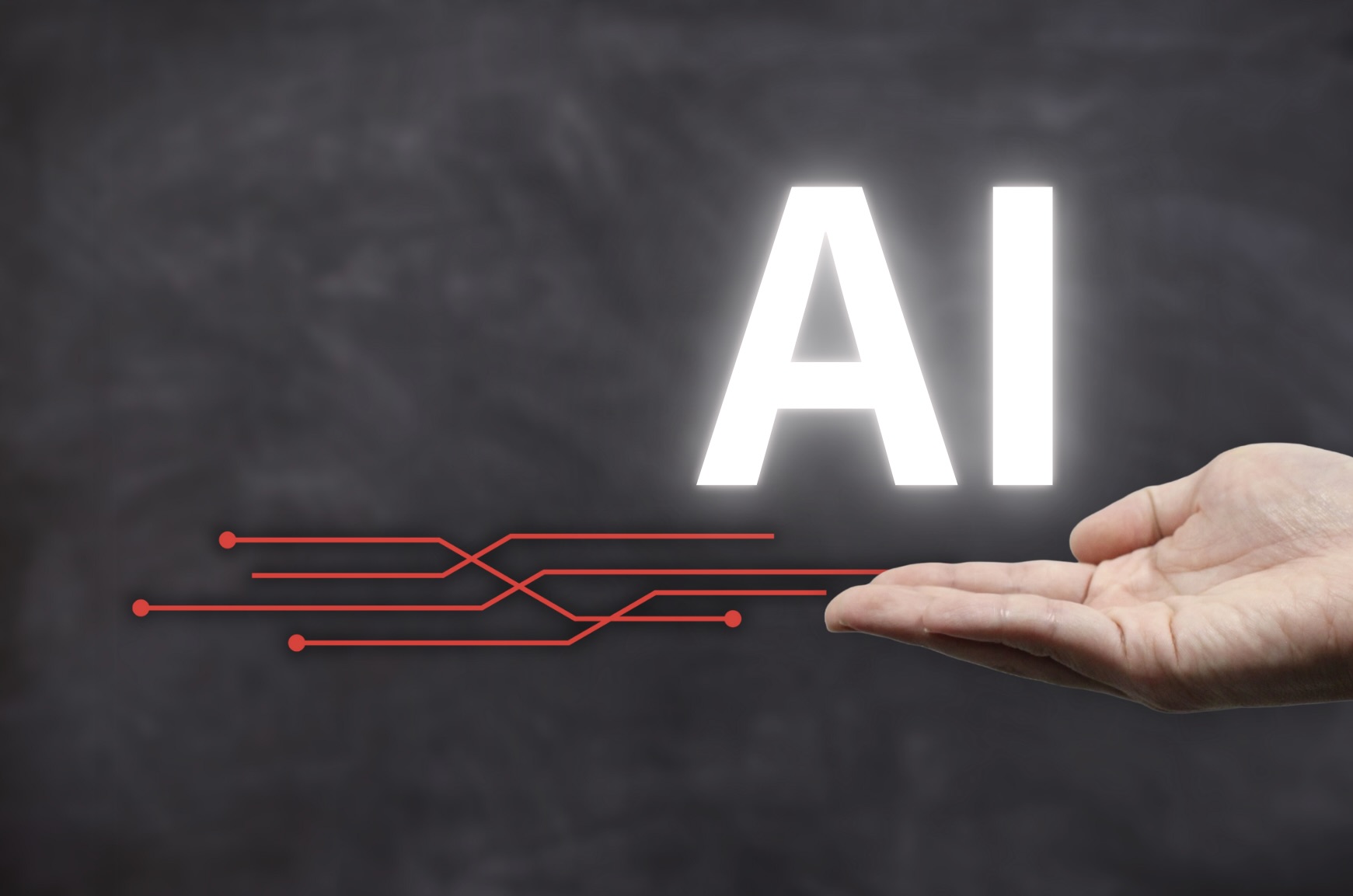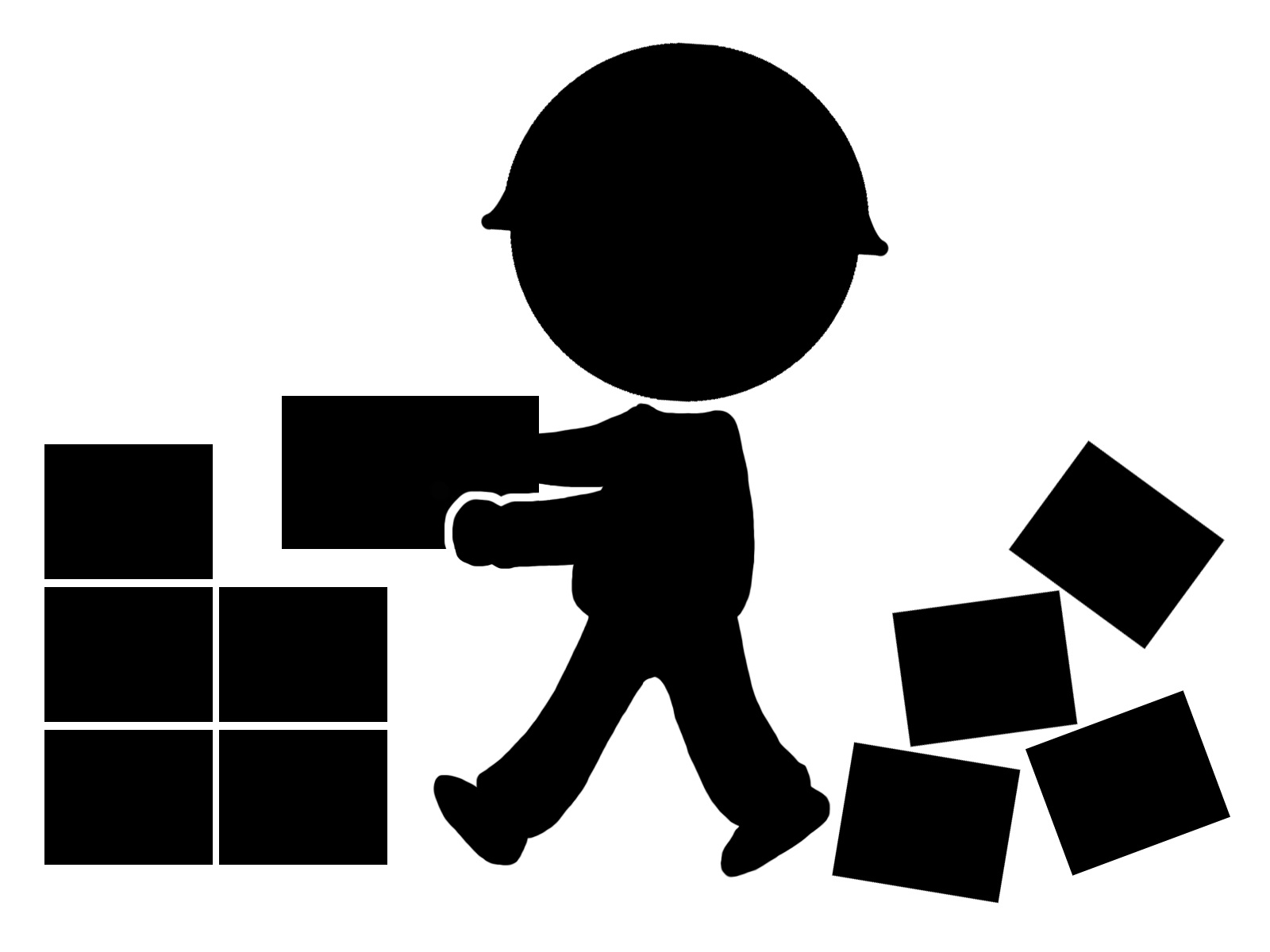少し前になりますが、某生成AIを使って簡単に「ジ〇リ風」など特定の作風に似せたイラストを生成できることが話題になりました。
自身の写真を元に「ジ〇リ風イラスト」のアイコンを作ったり、オリジナルの「ジ〇リ風」イラストやショートアニメを作ったりする人が多かったので、一度はどこかで目にしたことがあるのではないでしょうか。
話題になる一方で、「これって著作権的に問題ないの?」「クリエイターさんの作風にタダ乗りできちゃうってどうなの?」と思われた人も多いようです。
ということで、今回の「ちょっとした著作権の話」第10弾は、生成AIを利用した場合も含めて、改めて「〇〇風」のイラストや文章を作成する場合の注意点などを素人なりにまとめてみました。
あ、マルワのシャドーサイドあれこれ担当です。
あくまでも素人まとめのため、必ずしも法的に正しい解釈ではない事項が含まれている場合があることを予めご了承いただき、〇〇風イラストや文章の作成・公開はあくまでも自己責任でお願いいたします。
そもそも「作風」は著作権で保護されるのか?
特定の作品に登場するキャラクターそのものではなく、作家さん固有の「作風」をマネすること(作風を似せたオリジナルキャラ作成など)が、著作権侵害になるのかどうかというと……
日本の著作権法において、作風を真似ただけでは著作権の侵害とはみなされません。
著作権が保護する対象=著作物とは「具体的に表現されたもの」であり、作風(画風)はあくまでも「抽象的なアイデア」とされるため、著作権による保護の対象にはなりません。
たとえ、パッと見て(読んで)、「〇〇っぽいね」と特定の作家や作品を思い浮かべられる程度に似ていたとしても、既存作品や作品に登場するキャラクターそのもの、またはそれらの「表現上の本質的な特徴※」の類似・模倣でない限り、基本的には問題ないとされます。
※表現上の本質的な特徴…特定の(具体的に表現された)イラストなど著作物の「創作性」が認められる表現上の特徴であり、特定のキャラクターを識別できる外見等の特徴をいいます。
当然ですが、既存の特定のキャラクターやイラスト、文章などを「そのまま」作成(複製)した場合は、著作権の侵害になり得ます。
また、キャラクターなどは商標登録されている場合もあり、該当する商用目的で「〇〇風」のキャラクター(イラスト)を使用すると、商標権の侵害にもなり得ます。
ということで、たとえ作風の類似が著作権侵害ではないとしても、安易にビジネス用途で「〇〇風」のイラスト(キャラクター)や文章を作成・利用することは控えたほうがよいのではないかと思います。
ちなみに、日本の著作権法では、生成AIの学習のために、既存の第三者の著作物を著作者の許可なく読み込ませることは権利侵害ではない、とされています。そのため、生成AIが「〇〇風」という指示を理解できる(学習している)こと自体は問題ありません。
あくまでも、利用する側の責任(モラル)ということになります(リスク回避のために、利用許諾を得た作品以外は学習に利用しないことを明言している生成AIサービスも増えつつあります)。
類似性と依拠性の問題
作風は著作権による保護対象外ということではありますが、生成AIを利用する場合、単なる作風の類似・模倣を通り越して、意図せずに特定のキャラクターなどの「本質的な特徴まで酷似したもの」や、場合によっては「そのまま」のものが生成されてしまい、気づかずに利用・公開することによって、結果的に他者の著作権を侵害してしまう可能性もあります。
自身が作成した、または生成AIに指示して作成したイラスト等が著作権の侵害になるかならないかの重要なポイントに「類似性と依拠性の有無」があります。
類似性はその名の通り、元となる著作物に似ているかどうか、です。
どれくらい似ているか=どれくらい元著作物の「表現上の本質的な特徴」が含まれているか、ということです。
もうひとつの「依拠性」は、「既存著作物を知っていて(意図的に)利用したかどうか」ということです。要は偶然似てしまっただけなのか、意図的に似せた(パクった)のか、ということ。
生成AIを用いて作成した場合、指示を出した人はその著作物の存在を知らない(依拠性がない)けど、生成AIは元著作物を学習している(=依拠性がある)場合があります。
このような場合の責任の所在について、利用規約に定められていることがあるので、利用前に確認しておきましょう。
なお、生成AIに「〇〇風のイラストを描いて」のように特定の作者や作品を指定して指示した場合は、指示した人にも「依拠性」が認められる場合があります。
つまり、「ジ〇リ風」というように特定の作者やキャラクターを名指ししてAIに指示しているということは、意図的に似せようとしているわけなので、万が一著作権などの問題が生じた場合に、「知らなかった」「偶然似たイラストをAIが作っただけ」といった言い訳は通用しないことになります。
利用する生成AIの選定時には利用規約をよく確認しましょう
個人的に作成するだけなら問題になることは少ないと思われますが、企業などで(商用、ビジネス目的で)利用する場合は不要なトラブル発生リスクを低減するためにも、利用する生成AIの選定には注意が必要になります。
生成AIによっては、特定の作家や作品名を指示に含めることで、そっくりなもの、または「それそのもの」を生成できてしまうものがあります。一方で、特定の作家名や作品名を指示に含めることを禁止している(そのような指示を受け付けない)ものもあります。
生成のための指示(プロンプト)や参照データについても、自分以外がAIを使って生成する際の学習データとしてそれらの情報が利用されるものもあれば、指示や参照データは学習には利用しないことを明記しているサービスもあります。
自社や取引先の秘密情報の漏えいリスクを考えれば、学習に利用されないもの(または設定によって学習させないようにできるもの)を選定しておいたほうがよいでしょう。
また、生成AIを著作権侵害や違法な目的のために使用することを禁止する旨はほぼすべての生成AIの利用規約に定められていますが、生成されたイラストなどの利用によって結果的に誰かの権利を侵害してしまった場合の責任の所在がどこにあるのか(利用者が負うのか、サービス提供者が負ってくれるのか)もサービスによって異なります。
生成AIをビジネスで利用する場合は、利用開始前にこれらのことをよく確認しておきましょう。
法的に問題なければそれでいいのか?
たとえ意図的ではなかったとしても、また、作風が似ている(同じ)だけで特定のキャラクターを模したものではなかったとしても、それを見た(知った)第三者がSNSなどで「パクリ」として晒し、炎上してしまうケースもあります。
いくら作風(アイデア)は著作権の対象外で法的に問題はない、といったところで、特定の作家や作品への「タダ乗り」ともいえる行為に嫌悪感を示す人も一定数います。
もちろん、作風をマネること自体は悪いことではありません。
ですが、練習(学習)のためではなく、自身の承認欲求を満たすためや、利益を得るため(商用)に作風をマネするとなると話は別、という感覚を多くの人は持っていると思います。
生成AIを使うにしても、使わないにしても、「〇〇風」のイラストや文章などを作成する場合は、そのような「人」の感情面にも配慮は必要で、どのようにするのが自分(自社)にとって最適解か、ということを考えなければなりません。
みんなやっているから、とか、流行っているから、といって安易に便乗するのは避ける方が無難といえます。
また、生成AIなどで簡単に「〇〇風」が作れることで、元の著作者(作家)に悪影響が出るようになれば、法制度が変わる可能性もゼロではありません。
法規制の改定や生成AIの利用規約の改定などにも注意していく必要もあります。
本日のまとめ
ということで、まとめると、
- 「〇〇風」という作風のみの類似・模倣だけでは著作権の侵害とはみなされない
- 生成AIを使ったイラストなどで著作権問題が生じた場合、「〇〇風」と指示をしていれば依拠性ありと判断される可能性が高い
- 企業などで生成AIを利用する場合、権利侵害への対処や責任の所在などを事前に確認しておく
- 生成AIに関する法規制や利用規約は今後変わる可能性はある
- 法的に問題なくても、人の感情として作風の類似・模倣は否定的に捉えられる可能性がある
以上を踏まえて、
企業などでは安易に作風を模倣した作品を公開するのは避けた方がいいかもしれない
ということになります。
簡単で便利なものにはリスクもある、ということは先月のここでのブログでも書いた通りです。
注意・配慮しつつ、有意義に活用しましょう。
……ということで本日の脳内DJのパワープッシュは、カナダのフォークトロニカユニット、I am Robot and Proudの “Lines in a Grid” です!
AIとロボットは別モノですが、なぜだか頭の中でこの曲がループして、電子的な音とアコースティックで柔らかな音が心地よく混ざり合っておりました。
余談ですが、ジャズ、ロック、パンク、ソウル、シューゲイザー、テクノ、エレクトロニカ……などの音楽の「ジャンル」として括られる特徴・作風もそれだけでは著作権の保護対象にはなりません。
そこが著作権で保護されて、最初に作った人が独占できてしまったら、文化的な発展には至らないですよね。
本日はこの辺で。