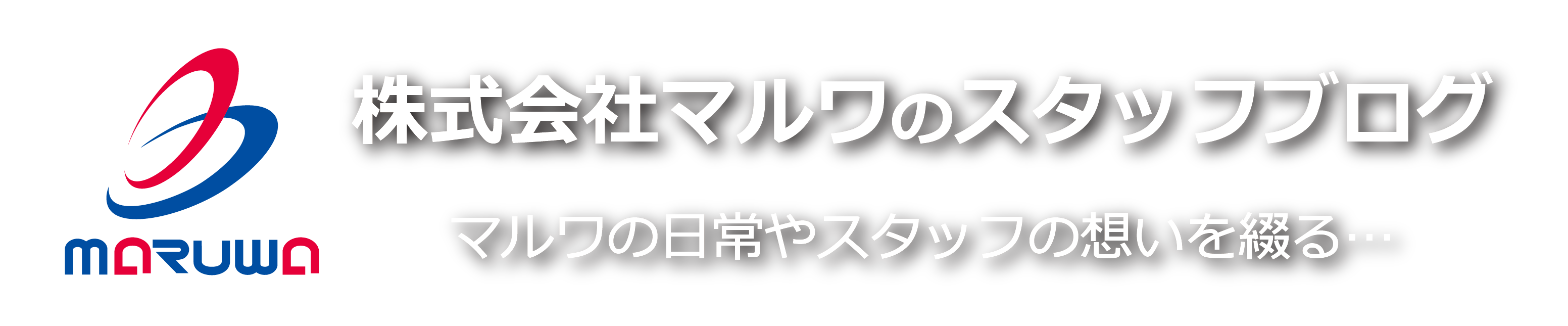ただいまマルワでは健康診断が真っ盛りで、順次スタッフが受診しています。かくいう私もつい先日の診断結果が届いて、昨年よりも悪化している項目が増えて、つくづく「健康第一」を肝に銘じた次第です。

さて、健康第一といえば、似たような語感で「安全第一」という標語があります。生産現場のある製造業や建設業では当たり前の言葉ですが、実はその続きで「〇〇第二」、「〇〇第三」があることをご存知でしょうか。
その答えが「安全第一、品質第二、生産第三」なのですが、生産工場や建設現場だけのものだと思っていませんか?実はこの言葉、私たちの暮らしや働き方すべてに深く関係しています。そして、そこに続く「品質第二、生産第三」という考え方にも、大切なメッセージが込められているのです。
たとえば、あなたがカフェでコーヒーを淹れるスタッフだったとします。丁寧にドリップし、美味しい一杯をお客さまに届けたい——これが「品質」にあたりますよね。でも、もし足元が濡れていて滑りやすい状態だったら?転んでけがをするかもしれません。コーヒーを落としてしまえば、お客さまにも迷惑がかかります。

つまり、どんなに良いものを作ろうとしても、自分自身が安全でなければそれは叶いません。「安全第一」とは、自分自身と周りの人たちの健康と命を守ることを最優先にしよう、という当たり前だけれど、つい後回しにしてしまいがちな原則です。
では「品質第二」はどういう意味でしょうか?けっして「品質はどうでもいい」という意味ではありません。安全を確保したうえで、初めて良いものが作れる、という順序を示しているのです。
第二次産業革命の頃、海外の工場では「生産第一・品質第二・安全第三」と言われていたそうです。従業員の安全よりも生産が重視されていたから、労務災害が頻発していたそうです。それに頭を悩ませた立派な経営者が、今の安全第一を打ち出したところ、安全性が高まっただけでなく、作業効率が良くなって、品質も生産性が向上していったそうです。
眠いけど車を運転する、熱があるけど出勤する——これらは「生産」を優先しすぎて「安全」をないがしろにした例と言えるかもしれません。
「安全第一、品質第二、生産第三」は、製造現場だけでなく、あらゆる仕事や日常生活において、自分を守りながら最善を尽くすというバランスのとれた考え方なのですね。マルワに限らず生産現場が稼働している日には社旗を掲揚する工場が多いですが、常に安全旗が一番上にあるのもこういった考えがもとになっているんですね。(写真だと分かりづらいですが)

家庭でも職場でも、まずは「安全」に目を向ける。それが結果的に、周囲への信頼や良い成果につながります。たとえば、お子さんが包丁を使いたがったとき、いきなり難しい料理に挑戦させるよりも、まずは正しい持ち方や安全な使い方を教えることが大切ですね。それと同じことが、仕事にも当てはまるのではないでしょうか。
コスパやタイパを求める時代だからこそ、「安全第一、品質第二、生産第三」を、あらためて意識しておきたいものです。そのうえで「健康第一、安全第二、・・・」ですね(^^♪