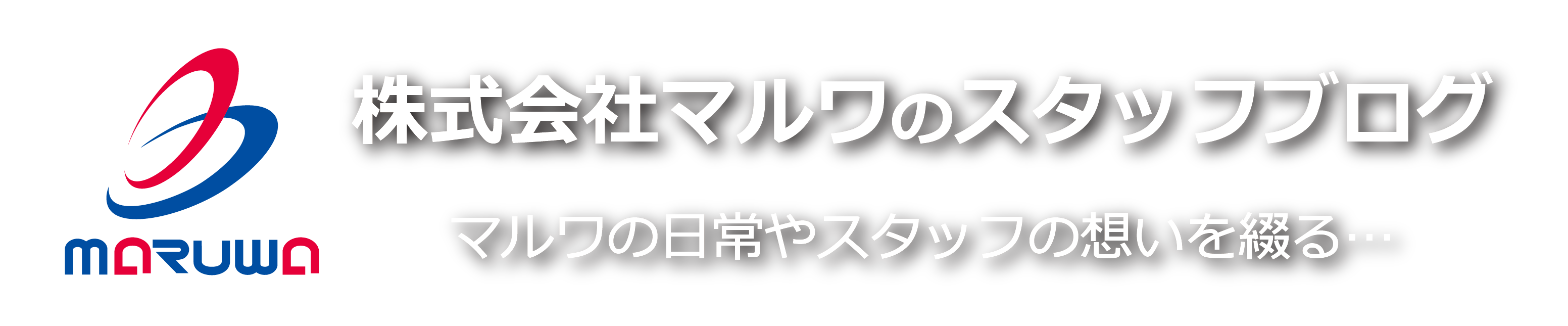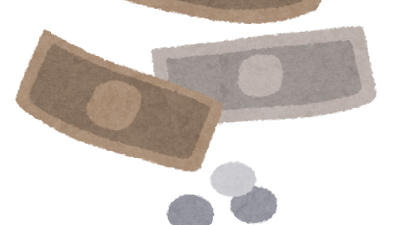印刷会社の法律ド素人が「それなり」に著作権についてまとめてみたシリーズの第9弾。
「著作権」については、何をすることはOKで、何をしたら権利侵害になるのか、判断に迷うことも多いと思います。
そのため、制作する人(クリエイターや制作会社)も、制作を依頼する人(クライアント)も、著作権を曖昧にしたまま契約&作成(納品)してしまうこともあり得ます。
ということで今回は、後々のトラブルを回避するために、クリエイター(制作会社)とクライアントが押さえておくべき著作権&契約のポイントをまとめてみました、という内容になります。
あ、マルワのシャドーサイドあれこれ担当です。
※本ブログは弁護士非監修のため、必ずしも法的に正しい解釈であることを保証するものではありません。ご了承ください。
★クリエイター&クライアントにありがちな著作権トラブル★
ケース① クライアントが無断で著作物を再利用した
例:パンフレット作成業務を依頼され納品したが、クライアントがパンフレット内に使用していたイラストを無断でデータ化(複製)し、Webサイトや広告などに使用した。
ケース② クリエイターが他者著作物を無断で使用した
例:クライアントに依頼されたチラシのビジュアルに、商用利用が禁止されているフリー素材の画像を使っていたため、使用差し止め請求がクライアントに届いてしまった。
ケース③ クライアントから事後に無償での著作権譲渡を要求された
例:契約ではパンフレットの作成・納品のみのはずだったが、納品後にパンフの中のイラストの著作権を無償で譲渡するようにクライアントから要求された。
このようなトラブルを防ぐためにも、次のようなポイントを押さえておきましょう!
ポイント① 著作権の基本を理解する
まずは、著作権の基本を押さえましょう。
| 1. 著作権は、自らが創作した作品(著作物)を独占的に利用することを認める権利です。 |
| そのため、他者の著作物を許可なく複製・改変・公開・販売などをすると権利侵害になります。 ただし、私的な利用(自分だけが使う場合など)のための複製、引用のための複製、学校教育に必要な複製など、著作権法で認められている例外(著作権の制限)の場合に限り、著作者の許可なく利用することができます。詳しくは文化庁WEBサイトの「著作権Q&A」をご参照ください。 |
| 2. 著作権は著作物を作成した時点で、制作者に自然発生する権利です。 |
| 著作権は著作物の制作者に認められる権利であり、他者に依頼して作ってもらった著作物の場合の著作権は、依頼者ではなく、制作者が保有することになります。 |
| 3. 著作権には人格権と財産権があり、財産権の全部または一部は他者に譲渡することができます。 |
| 財産権を譲渡された者はその権利を保有し、行使することができるようになります(人格権は譲渡されません)。 |
ポイント② 著作物に該当するもの・しないものを理解する
著作権は「著作物」に認められる権利であるため、著作物以外には適用されません。
著作物とは何か、についての定義は、著作権法第2条第1項第1号において、
- 思想又は感情を
- 創作的に表現した
- 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの
と、定められています。
ざっくりいうと、「人が創作した美術・芸術作品を含む殆どのコンテンツ(作品)」は著作物であり、著作権で守られる、と考えてよいでしょう。
【著作物の例】
| イラスト、絵画、写真、WEBや印刷物のデザイン |
| 楽曲、歌詞、楽譜 |
| 小説、ニュースや雑誌記事、ブログ、論文 |
| 映像、映画、アニメ |
| プログラム、ゲーム |
他方、上記のような作品であっても、「思想又は感情を」「創作的に表現」していないものは、著作物とは認められず、著作権による保護の対象になりません。
| 思想又は感情を表現していないもの |
| ・単なるデータ、歴史的な事実のみ ・人が創作に加担していないもの(動物が偶然撮った写真など) |
ただし、「歴史的事実を基にして創作された歴史小説(漫画)」「データの集積に特定のルールを用いていいる(創意工夫が含まれる)データベースや資料」「データの見せ方に創作性が認められるグラフなどの表現」は著作物に該当します。
また、「人が創作に加担していない」について、生成AIでイラストや写真、文章などを作成した場合の著作権の考え方は「創作(操作)に人が加担しているとみなされるため、通常の著作物同様の判断基準が適用される」とされています(2025年5月現在)。
| 創作的な表現が含まれないもの |
| ・頭の中にあるだけのアイデア(カタチになっていないもの) ・作風、企画、設定、レイアウトや配色などのみ ・ありふれた表現(タイトルや見出しなどの短い表現もこれに該当) ・他者著作物の模倣物(パクリ)、または他者著作物を無断で使用しているもの(元作品の制作者の著作物であり、自身の著作物とは認められない) |
設定やレイアウト、作風、タイトルなどは著作権の保護対象とはみなされません。ただし、配色やタイトルなどは商標登録されていれば、商標権で保護されます。
そのため、自分で考えたアイデアやレイアウト、タイトルなどが、他者に真似された(勝手に使われた)としても著作権侵害とはみなされない可能性が高いということになります。
ポイント③ 他人の著作物は許可された範囲を超えて利用できない
著作権は、「自らの著作物を独占的に利用することを認める権利」であるため、他者の著作物を使用するためには、著作者の許可・承諾が必要になります(著作権法による例外の場合は除く ポイント①参照)。
そのため、他者の著作物を利用する場合、著作者との契約内容や、著作者側が定める利用規約に定める利用方法(利用範囲)を超えて利用することはできません。
具体的には、次のような行為は、著作者の許可を得られていない(規約に規定がない、または禁止されている)のであれば、絶対にやってはいけません!
| 許可なく公開(公表)すること |
| 作者名を勝手に決めて公開(公表)すること |
| 自分の著作物であると偽って公表すること |
| 許可なく改変すること(ストーリーの変更、キャラクターの容姿の変更、タイトルの変更など) |
| 許可なく複製して販売、配布、ネット上への公開などをすること(コピー品の販売、コピーデータのネット上への公開など) |
| 許可なく商標などに登録すること※ |
| 許可なく二次創作物を作成すること(チラシをポスターにする、キャラクターグッズを作る、作品の登場人物を使用した独自作品を公開するなど) |
ポイント④ 契約内容を確認する
著作物作成の業務委託(制作依頼)をする場合、または著作物利用の許諾を得る場合は、契約形態とその内容を事前に確認し、著作権の所在や著作物の利用可能範囲を明確にしておくことが重要です。
ケース① 通常の業務委託・制作依頼の場合
クリエイター(制作会社)が著作権を保有します。
クリエイター(制作会社)は、依頼された物品またはサービス(データ)をクライアントに納品し、クライアントは、納品された物品またはサービス(データ)を、クリエイター(制作会社)と事前に合意した範囲内で利用できます。
例:A4サイズのチラシ作成のみを依頼した場合、クライアント側がチラシをエンドユーザーに配布することはできますが、クリエイターの許可なくチラシをA1サイズのポスターに拡大複製して利用することはできません。
ケース② 利用許諾・ライセンス契約の場合
クリエイター(サービス提供者)が著作権を保有します。
利用者は、クリエイター(サービス提供者)が許可する目的・利用方法の範囲内で、著作物(サービス)を利用できます。
特にクリエイター(制作会社)がクライアントからの依頼で何らかの著作物を作成する場合で、制作物に他者著作のイラストや写真素材、書体などを使用する場合は、必ず利用規約などを確認しておきましょう。
万が一納品した著作物の中で権利侵害があった場合、クリエイター本人ではなくクライアント側にクレーム(利用差止請求)がきてしまうおそれがあるので注意しましょう。
例:イラスト素材の提供サービスの利用ライセンス契約を締結して利用する場合、利用規約で商用利用が禁止されている素材を商品の一部に利用することはできません。
ケース③ 著作権を譲渡する契約の場合
クライアントが譲渡された著作権を保有します。
譲渡された権利はクライアントに移行します。譲渡された者は、制作者の許可を得ずに譲渡された権利(複製や改変などの権利)を行使することができます。
著作権の譲渡が必要な場合は、双方合意のうえで譲渡契約を締結しましょう(著作権譲渡契約については過去記事(ちょっとした著作権の話⑥)もご参照ください)。
ただし、著作権のうちの「人格権」は譲渡する事ができない権利なので、著作物の改変や公表時の名称をクライアントが変えたい場合などでは、譲渡契約書に「人格権を行使しないこと」「著作権法第27条と第28条も譲渡される権利に含むこと」を明示して双方合意しておきましょう。
また、お互いの要望(譲渡してもらう目的、最低限守ってもらいたいルール、対価など)について、漏れなく確認して合意しておくことで、後々のトラブルを予防できます。
まとめ:クリエイターとクライアントがすべきこと
| 項目 | クリエイターがすべきこと | クライアントがすべきこと |
|---|---|---|
| 著作権の理解 | 自身の権利を知る、作成時にやってはけないことを知る | 制作者の権利、自らが許可されることを知る |
| 契約書 | 契約内容を確認する | 契約内容を明確に提示する |
| 使用範囲 | クライアントと事前に合意しておく | 必要な権利を確保する(改変が必要なら著作権譲渡契約を締結する) |
著作権を正しく理解することで、クリエイターも安心して仕事ができますし、クライアントも安心して仕事を依頼できるはずです。
そのために、抑えるべきポイントをしっかり押さえておきましょう!
そんなこんなで本日の私の脳内DJのパワープッシュは、Corneliusのライブ定番インスト曲の“Another View Point”です!
物事には自分が見ている(見えている)のとは別の見え方もあります。
著作物&著作権も、作る側と使う側では見え方が違っていると思います。
お互いにとって有益な制作&利用になるよう、押さえるところは「事前に」確認しておきましょう。
本日はこの辺で。