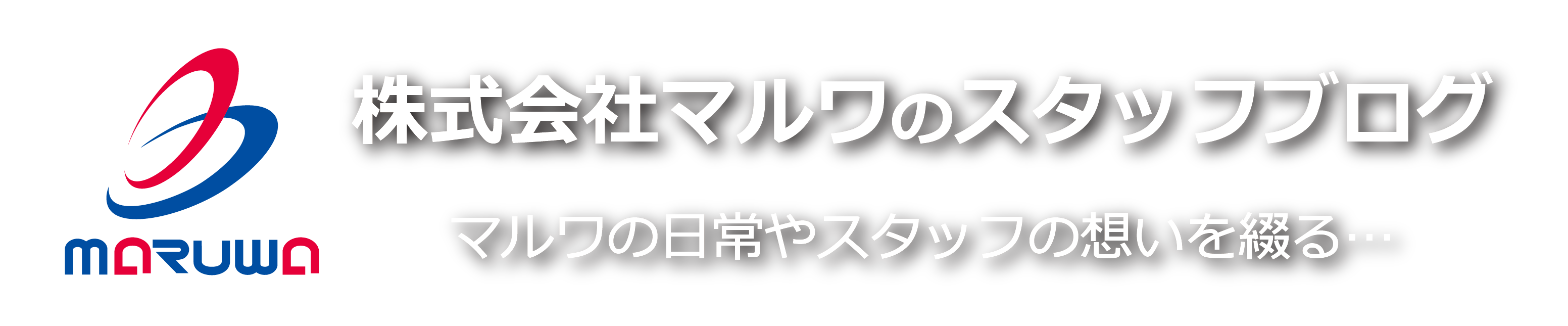こんにちは。オンデマンド機担当のOです。
先週は経営計画発表会、今週はインターンシップがあり、なんとなく今思っている事をAIの力も借りつつ学生さん向けに書いてみたくなりました。
では早速本題に入りますが、愛知県豊明市が「スマートフォン利用2時間以内」の条例案を提出して話題になっていますね。
この条例の特徴は、罰則がない「強制力のないルール」だということです。
実は、このような「強制力のないルール」は会社でもたくさん存在していて、私たちの働き方に大きな影響を与えています。
職場にある「強制力のないルール」って?
まず、職場にどんな「強制力のないルール」があるか見てみましょう。
会社の行動規範・企業理念
多くの会社には「お客様第一主義」「チームワークを大切に」といった理念があります。これを破ったからといってクビになるわけではありませんが、社員の行動の指針になっています。
会社でよくある暗黙のマナー
- 会議には5分前に到着する
- メールの返信は24時間以内に
- 残業している人に「お疲れ様」と声をかける
これらは多くの場合就業規則には書いていませんが、職場で当たり前とされているルールです。
労働時間の「目安」
豊明市の条例と同じように、「残業は月30時間以内を目安に」「有給休暇は年10日以上取得しよう」といった数値目標も、必ずしも強制力があるわけではありません。
なぜ強制力がないのに効果があるの?
1. みんなが見ているプレッシャー
罰則がなくても、同僚や上司が見ているという意識が働きます。「みんなが頑張っているのに自分だけ」という気持ちになりやすいのです。
2. 会社への所属意識
「この会社の一員だから、会社の方針に合わせよう」という気持ちが自然と生まれます。これは学校で校則を守るのと似ています。
3. 評価への影響
直接の罰則はなくても、人事評価や昇進に影響する可能性があります。これが見えない強制力として働くのです。
仕事への具体的な影響
プラスの影響
チームワークの向上 「協力しよう」という理念があることで、自然と助け合いの雰囲気が生まれます。
自己管理能力の向上 「残業時間の目安」があることで、効率的に仕事を進めるスキルが身につきます。
働きやすい環境作り 「ハラスメント禁止」といった方針があることで、みんなが過ごしやすい職場になります。
マイナスの影響
曖昧さによる困惑 「どこまでやればいいのか分からない」という状況が生まれることがあります。
人によって解釈が違う 上司と部下で「目安」の受け取り方が違い、トラブルになることもあります。
見えないプレッシャー 表面上は自由でも、実際には強いプレッシャーを感じてストレスになる場合があります。
まとめ
法学の世界では、法的拘束力を持たない規範を「ソフト・ロー(soft law)」と呼びます。
「強制力のないルール」は、一見すると曖昧で分かりにくいものです。
でも実際の職場では、このようなルールがとても重要な役割を果たしています。
大切なのは:
- ルールの意図を理解すること – なぜそのルールがあるのかを考える
- 自分で判断する力を身につけること – 答えが明確でない状況で適切に行動する
- 周りとのコミュニケーションを大切にすること – 困ったときは相談する
「暗黙の了解」と聞くと排他的であまり良いイメージでは無いかもしれませんが、悪い事ばかりではありません。
豊明市のスマホ条例も、内容はともかくとして「デジタル時代をどう生きるか」を考えるきっかけだと思います。
皆さんも今一度身の回りのルールについて考えてみてはいかがでしょう?