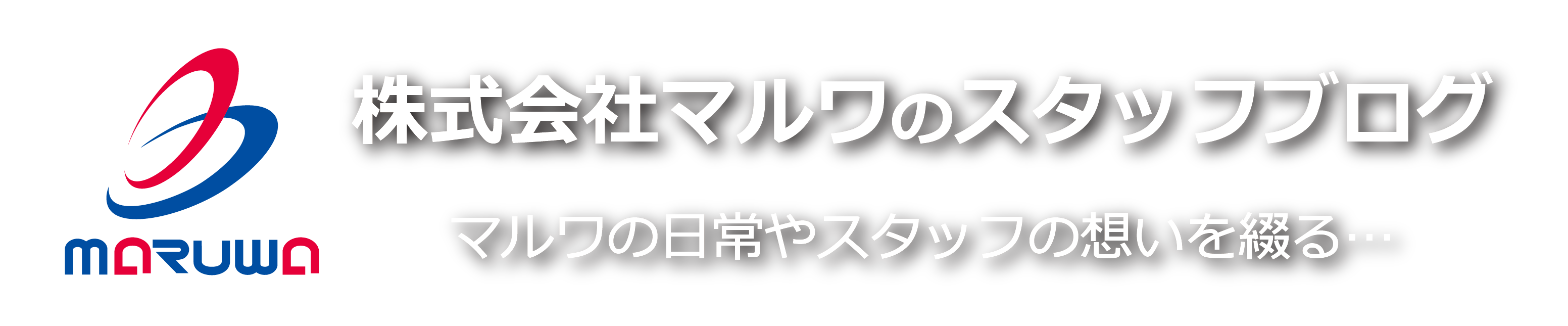防災の標語といえば、皆様はどのような言葉を思い出されるでしょうか。
小学校の避難訓練で「お・は・し」と教わった方も多いのではないかと思います。
地震や火災といった災害時に、慌てずに安全に避難するための行動を促す標語として、長らく「お・は・し」が使われてきました。
これは「押さない・走らない・喋らない」の頭文字を取ったもので、混乱や二次被害を防ぐための行動をとるための標語です。
東日本大震災や能登半島大地震、豪雨災害など少しずつ災害が増えている中で、時代とともに防災意識も高まり、より実践的な行動を促すために「お・は・し・も・ち」へと発展しているそうです。
「も」は「戻らない」。一度避難したら安全確認のないまま現場に戻らないこと。
「ち」は「近づかない」。火元や倒壊の恐れがある建物など、増水している川など危険な場所には安易に近づかない意識を持つこと。
そのような意味合いで追加されいているそうです。
「お・は・し・も・ち」
聞くと懐かしい防災標語。子どもから大人まで、誰もが理解しやすく、記憶に残りやすいこの言葉を通じて、日常から防災意識を高め、いざというときの行動の助けになればと思います。