数か月前から、無性に読みたいと思う本がありました。以前に読んだのは数十年も前、あらすじも大まかにしか覚えておらず、当時高校生だった私には何となく怖い話という印象だけが、インプットされ続けていた本です。
それは、阿部公房の「砂の女」。再読してみるとあらすじはこうでした。
教師である主人公は趣味の昆虫採集のために海岸の砂丘に行きます。そこには今にも砂に埋もれそうな村があり、最終バスに乗り遅れた主人公は、村人に騙され、砂穴(地上までは10メートル以上)の中の家に住む女とともに閉じ込められてしまいます。
村の中の10数件の家は穴に埋もれ、毎日穴から砂を運び出さなければ崩れてしまうため、時折訪れる村外の人間を砂掻きの人手としていたのでした。穴の中の生活は夜砂かきを行い、昼間は就寝。一日一回水や食料が支給されるというもの。
女と暮らすことになった主人公は、最初は女や村人を説得し、開放してくれるよう懇願したり、村から出て別の生活をするよう説得したりしましたが、女も村人も自分たちが住む集落を守ることしか興味はなく、主人公の話に耳を貸すものはいませんでした。
なんとか自力で縄梯子を作り、一度は脱出した主人公でしたが、逃走中に砂に埋もれ動けなくなった所を村人に助けられ、再び女の家へ戻されます。
一度逃げ出した主人公に対して村人が取ったのは、砂かき作業をするまで家への水の配給を絶つという手段。あまりの喉の渇きに耐えかねた主人公は砂かきを開始。しばらくは波風を立てないようにと穴の中で真面目に砂を掻いて過ごし、女とも夫婦のように暮らし始めます。(主人公を穴に戻した村人は、決して暴力的なことはしません。やさしく、主人公が必要な物は調達してくれるます)
そんな暮らしの中で主人公の目標となったのが砂の中で水を確保するための、溜水装置の開発。改良を重ね、少しずつ成果が出てきた頃、女が病気になり、病院へ搬送されます。その時、村人が回収し忘れたのか、外に出るための縄梯子がそのままになっていました。しかし、男は脱走しようとはせず、自分が開発した溜水装置について村の者に話したいという思いでいっぱいになっていました。いつしか主人公は村の一員になっていたのでした。
という話です。
なぜ最近になって記憶の奥底にあったはずの『砂の女』を読みたくなったのか、それは多分「コロナ禍」の私たちの生活とどこか重なる気がしたのだと思います。
砂穴の家は「コロナ禍の社会」。コロナウイルスに対する恐怖心を植え付けられた私たちは、感染者が増えないように新しい生活様式という名の行動制限を守り暮らします。ルールさえ守って暮らせば社会は優しいですが、そのルールに反発したり、うっかりコロナウイルスに感染すれば、人々の白い目にさらされ、誹謗中傷、いじめ、差別の対象となる可能性があります。そんな不自由と感じている社会の中でも、いつの間にか慣れてしまい、『砂の女』の主人公のように、異常とか不自由とか思わなくなる日が来るかもしれません。なんだか怖いですが。
縄梯子(ワクチンや治療法、共存?)がかけられた時、どのくらいの人が登ることができるでしょうか。
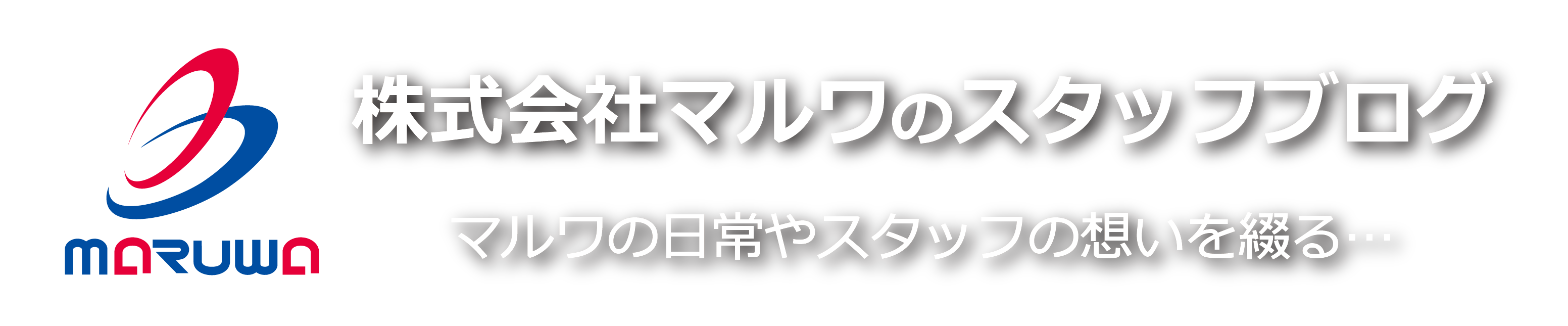



コメント